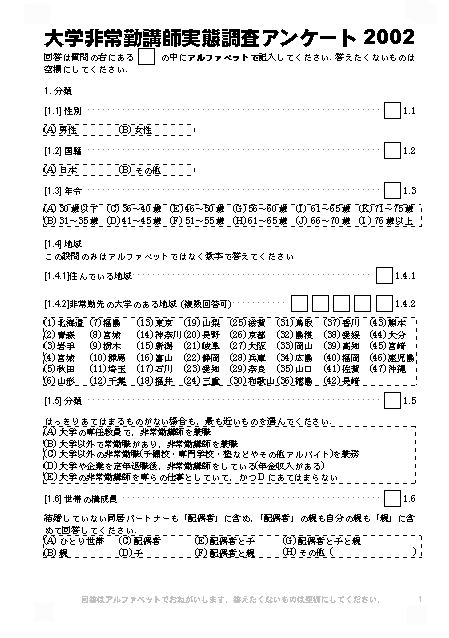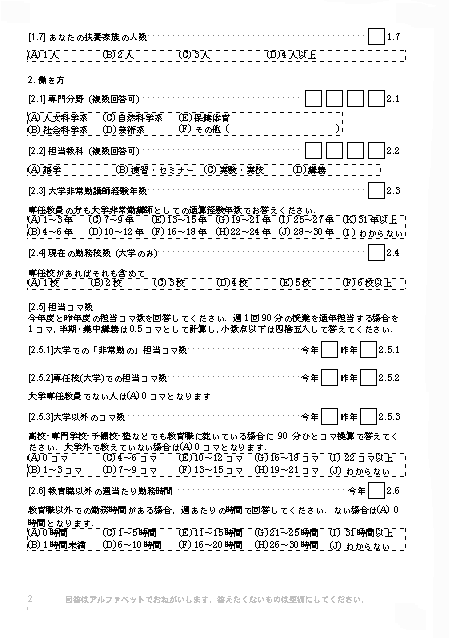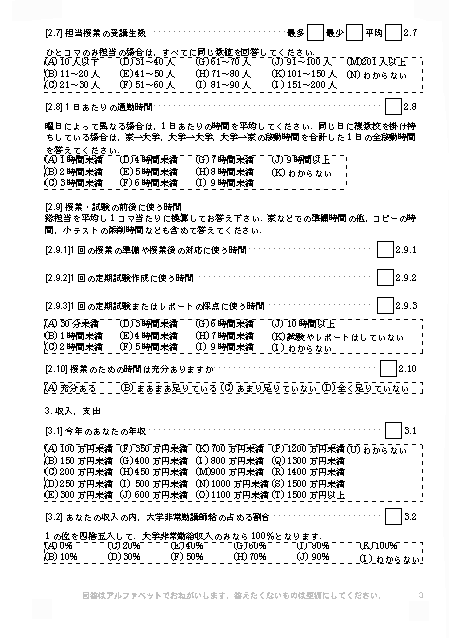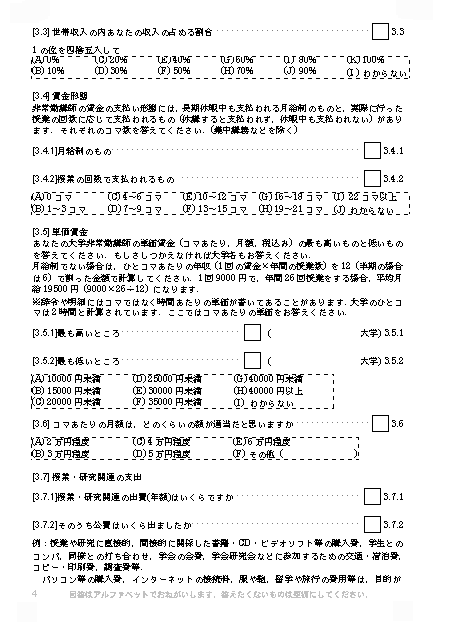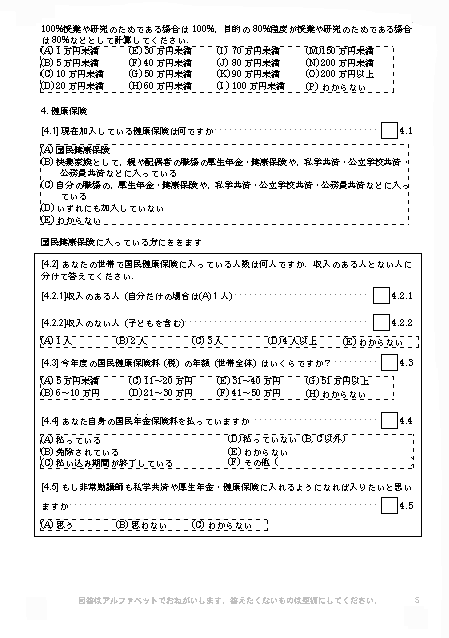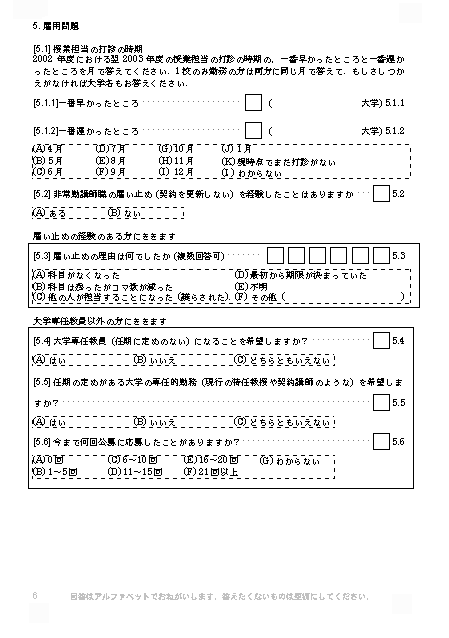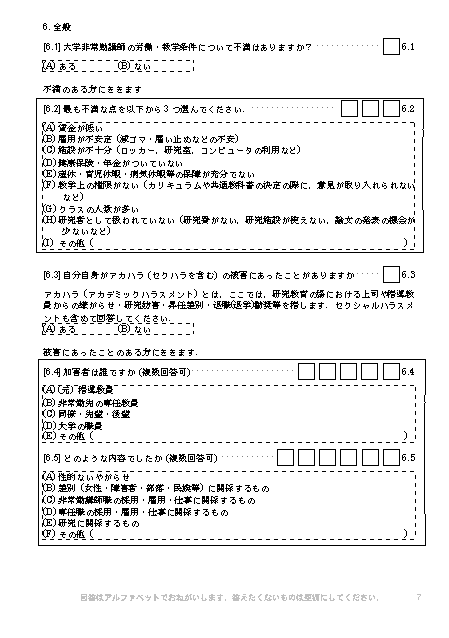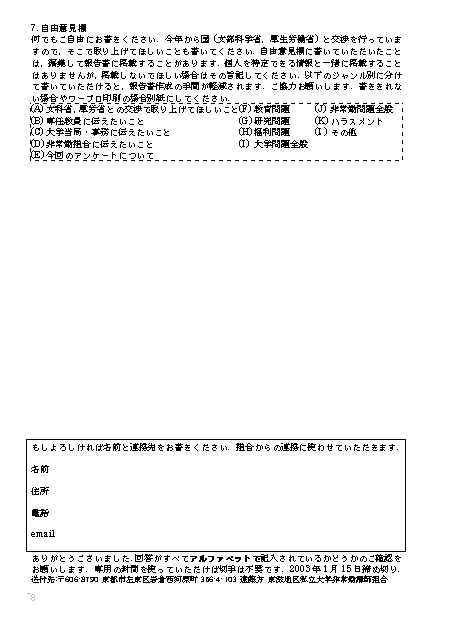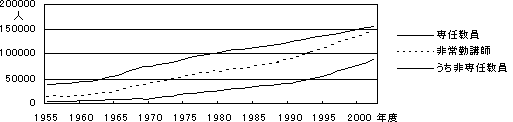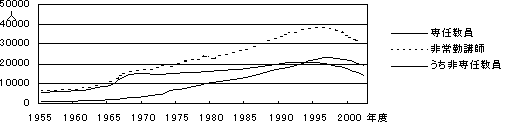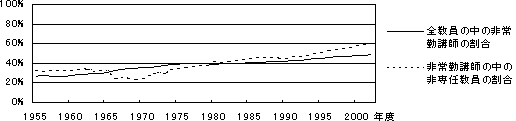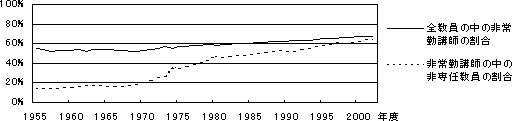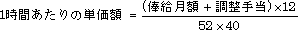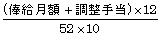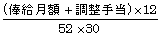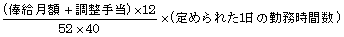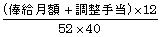アンケート用紙
テキスト版は
こちらをごらんください.
私立大学等への経常費助成の仕組み
日本私立学校振興・共済事業団の「私立大学等経常費補助金取扱要領」と「私立大学等経常費補助金配分基準」 (ここでは2002年3月版を使用) は,経常費国庫助成の基本事項を定めている.非常勤教員に関するものも含まれる.(助成の基本的仕組みは1982年以来,固定されていると聞く.)
「取扱要領」によれば,補助金が交付される「経常的経費の範囲」は次の7項目である.
- (1) 専任教員等給与費 (給与,退職金に係る経費)
- (2) 専任職員給与費 (給与,退職金に係る経費)
- (3) 非常勤教員給与費 (給与に係る経費)
- (4) 教職員福利厚生費 (専任教職員の労災保険,私学共済・厚生年金等に係る経費)
- (5) 教育研究経常費 (学生教育,専任教員の研究,専任教職員の研究のための外国旅行,社会人教育,非常勤教員の研究に係る経費)
- (6) 厚生補導費 (学生指導,課外教育,保健管理,学生指導・課外教育のための内国旅行,学生指導のための研修会,私立大学奨学事業に係る経費)
- (7) 研究旅費 (専任教員の研究のための内国旅行に係る経費)
これら7項目は教員に注目して次表に整理できる.但し,非常勤教員の(5)は名目的で,次に見る「配分基準」の計算式で考慮されている訳ではない.
| 区分 | 人件費に関わる項目 | 教育研究に関わる項目
| | 専任教員等 | (1)(4) | (5)(6)(7)
| | 非常勤教員 | (3) | (5)
| |
「配分基準」によれば,経常的経費に関する補助金額を見積もるにあたり,まず「経常的経費の算定」を行う (次頁の表「私立大学の場合の経常費補助金の計算式」参照).こうして得られた金額に,(3) 非常勤教員給与費と (4) 教職員福利厚生費は0.4を,それら以外は0.5を乗じることにより,補助金の「基準額」が得られる.この基準額は,調整係数 (α,βとおく) を乗じることにより6〜140%の範囲に「調整」される.少し前まで調整係数は一つ (0.5〜1.3) だったが,今では二つに分けられ,やや下方修正された.(調整係数α:「0.2〜1.4」.定員に対する在籍学生数,専任教員あたりの在籍学生数,学生納付金収入に対する教育・研究・設備面の支出の割合により,別表から定まる.学生定員を守る,学生納付金を学生に還元する割合が高い等の場合,最大値に接近する.調整係数β:現時点ではβ=αに見えるが,いずれ異なる値になるのだろう.)
以上により計算された「調整済み金額」は,次のように所定の金額を最終的に調整される: 【減額】 個々の専任教員等・専任職員・役員の年間給与等が所定の額より高いとき減額; 【減額】 学校法人が支出した寄付金の合計額が所定の額 (3000万円) より多いとき減額; 【調整】 改組学部等に関わる学生定員振り替えに伴い増減の調整; 【増額】 私立大学奨学事業,高度化・情報化・国際交流・生涯学習・大学改革の事業で増額; 【減額】 事業団からの借入金償還の滞納,争議・授業放棄その他の著しく不正常なとき減額.こうして最終的に調整した合計額が交付 (申請) 補助金の額となる.
非常勤教員に関わる別記5について
非常勤教員に直接関わる部分は「非常勤教員給与費」と別記5である.別記5「2.(1)」の式は,1コマ90分 (2授業時間) を通年で30回こなすと考え,2×30=60で割ってコマ数に換算すると
((専任教授数+専任講師数)×5+専任助教授数×4.5)×0.3337 (コマ)
となる.ここで例えば専任教授3,専任助教授2,専任講師1の場合,上の式に代入すると,次が得られる.
((3+1)×5+2×4.5)×0.3337=29×0.3337=9.6773 (コマ)
この式では,非常勤教員給与の補助金は,専任教員6人に対し通年科目で10コマ弱 (専任教員1人当たり1.6コマ) が交付対象 (上限) である.このようにして求めた授業時間数と,実際に非常勤教員が担当する授業時間数とを比べ,小さい方が,(3)非常勤教員給与費の補助金を求める式の「非常勤教員の授業時間数」となる.
私立大学の場合の経常費補助金の計算式 (最終的な調整の直前までの計算式)
| 区分 | 経常的経費の算定 | 基準額 | 調整
| | (1) 専任教員等給与費 | 【給与】標準給与費5731千円×専任教員等数 | ×0.5 | ×α
| | 【退職金】標準経費349千円×専任教員等数 | ×0.5 | なし
| | (2) 専任職員給与費 | 【給与】標準給与費3601千円×専任職員数 | ×0.5 | ×β
| | 【退職金】標準経費218千円×専任職員数 | ×0.5 | なし
| | (3) 非常勤教員給与費 | 標準経費3.4千円×非常勤教員の授業時間数 (別記5) | ×0.4 | ×β
| | (4) 教職員福利厚生費 | 【労災保険】教員標準経費17千円×専任教員等数+職員標準経費10千円×専任職員数 | ×0.4 | なし
| | 【私学共済等】教員標準経費244千円×専任教員等数+職員標準経費152千円×専任職員数 | ×0.4 | なし
| | (5) 教育研究経常費 | 専任教員等1人当たり校費×専任教員等数+学生1人当たり校費×学生(定員)数 | ×0.5 | ×α
| | (6) 厚生補導費 | 【(学生経費)】3.9千円×学生(定員)数+1千円×通信教育学生数 | ×0.5 | ×β
| | 【私立大学奨学事業】利息軽減措置額+0.8千円×新規対象学生数 | ×0.5 | なし
| | (7) 研究旅費 | 1人当たり研究旅費 (実験系74千円,非実験系80千円)×専任教員等数 | ×0.5 | ×α
| | 調整済み金額 | 上記(1)から(7)の計算式による合計額
| |
別記5: 非常勤教員の範囲及び授業時間数の算定方法
|
1.非常勤教員の範囲: 非常勤教員のうち,1授業時間当たり平均給与として,大学では1800円以上,短期大学と高等専門学校では1600円以上の額を支給される者
2.「非常勤教員の授業時間数」の範囲: 次のうちの小さい方
(1) ((専任教授数+専任講師数)×300+専任助教授数×270)×0.3337授業時間
(2) 実際に非常勤教員が担当する授業時間数
| |
参考: 実際に経常費助成はいくら出ているか
経常費助成金の大学別総額は私学振興事業団のホームページ (http://www.shigaku.go.jp) で公開されていますが,内訳までは掲載されていません.しかし,法人文書開示制度に基づいて申請すれば内訳も公開されます.
例えば,京都4大学 (立命館, 同志社, 龍谷, 京都産業) の2001年度の補助金の内訳は以下の通りです.専任と非常勤講師の人数と担当コマ数は京滋非常勤組合と京都4大学との交渉の中で明らかになったものです.
実際に支給されている額は,専任は,ひとりあたり年100〜140万円,ひとコマあたり年15〜25万円であるのに対して,非常勤は,ひとコマあたり年1.3万円〜1.9万円です.コマあたりの額は,専任と非常勤で8〜17倍もの差があります.また,京都4大学での非常勤講師担当コマは全体の25〜40%なのにもかかわらず,非常勤講師の給与に対する補助金は,専任の給与に対する補助金の3〜4%,補助金全体の1〜1.3%です.
2001年度補助金費目別確定額 (単位:千円)
| | 立命館 | 同志社 | 龍谷 | 京都産業
| | 教員給与費 | 1,110,117 | 26.6% | 645,880 | 23.8% | 530,041 | 29.4% | 295,148 | 28.7%
| | 教員退職金掛金 | 81,676 | 2.0% | 66,853 | 2.5% | 53,364 | 3.0% | 41,505 | 4.0%
| | 職員給与費 | 513,579 | 12.3% | 207,402 | 7.6% | 186,191 | 10.3% | 133,369 | 13.0%
| | 職員退職金掛金 | 32,086 | 0.8% | 26,204 | 1.0% | 21,481 | 1.2% | 19,630 | 1.9%
| | 非常勤教員給与費 | 43,120 | 1.0% | 28,111 | 1.0% | 23,392 | 1.3% | 13,378 | 1.3%
| | 教職員福利厚生費 | 106,670 | 2.6% | 63,077 | 2.3% | 54,012 | 3.0% | 40,774 | 4.0%
| | 教育研究経常費 | 2,243,563 | 53.7% | 1,647,053 | 60.7% | 913,319 | 50.6% | 473,136 | 46.0%
| | 厚生補導費 | 28,532 | 0.7% | 22,147 | 0.8% | 14,348 | 0.8% | 7,409 | 0.7%
| | 研究旅費 | 15,141 | 0.4% | 8,833 | 0.3% | 7,137 | 0.4% | 3,771 | 0.4%
| | 計 | 4,174,484 | 2,715,560 | 1,803,285 | 1,028,120 |
|
ひとり当り,ひとコマ当り補助金
| | 給与費補助金 | 人数 | ひとり当り補助金 | コマ数 | ひとコマ当り補助金
| | 立命館 | 専任 | 1,110,117千円 | 825人 | 1,346千円 | 4,486コマ (65.7%) | 247千円
| | 非常勤 | 43,120千円 | 1165人 | 37千円 | 2,345コマ (34.3%) | 18千円
| | 同志社 | 専任 | 645,880千円 | 464人 | 1,392千円 | 3,246コマ (60.7%) | 199千円
| | 非常勤 | 28,111千円 | 915人 | 31千円 | 2,099コマ (39.3%) | 13千円
| | 龍谷 | 専任 | 530,041千円 | 415人 | 1,277千円 | 2352コマ (56.6%) | 225千円
| | 非常勤 | 23,392千円 | 1437人 | 16千円 | 1800コマ (43.4%) | 13千円
| | 京都産業 | 専任 | 295,148千円 | 292人 | 1,011千円 | 1,911コマ (73.5%) | 154千円
| | 非常勤 | 13,378千円 | 250人 | 54千円 | 690コマ (26.5%) | 19千円
| |
設置機関別に見た非常勤講師の数と比率
| 年度 |
教育研究機関 |
専任教員
A (人) |
兼任講師
A* (人) |
専任教員の兼任率
A*/A |
非常勤講師
B (件) |
兼任講師
C (件) |
兼業講師
D (件) |
専業非常勤講師
E (件) |
非常勤講師の比率
B/A |
兼任講師の比率
C/A |
兼業講師の比率
D/A |
専業非常勤講師の比率
E/A
| | 1974 | 総 計 | 98835 | - | - | 69589 | - | - | - | - | - | - | -
| | 1977 | 総 計 | 119608 | 30301 | 0.253 | 82085 | 49042 | 10186 | - | 0.686 | 0.410 | 0.085 | -
| | 1980 | 総 計 | 123934 | 37376 | 0.302 | 81775 | 46588 | 35187 | - | 0.660 | 0.376 | 0.284 | -
| | 1983 | 総 計 | 131069 | 36887 | 0.281 | 98358 | 47405 | 41424 | - | 0.750 | 0.362 | 0.316 | -
| | 1986 | 総 計 | 136485 | 41579 | 0.305 | 111734 | 50711 | 29973 | 27328 | 0.819 | 0.372 | 0.220 | 0.200
| | 1989 | 総 計 | 145614 | 45367 | 0.312 | 123545 | 57961 | 40708 | 24768 | 0.848 | 0.398 | 0.280 | 0.170
| | 1992 | 総 計 | 157331 | 47772 | 0.304 | 140373 | 63587 | 47275 | 29502 | 0.892 | 0.404 | 0.300 | 0.188
| | 1995 | 総 計 | 165775 | 49871 | 0.301 | 159392 | 67029 | 40510 | 51853 | 0.961 | 0.404 | 0.244 | 0.313
| | 1998 | 総 計 | 170939 | 48450 | 0.283 | 173542 | 67410 | 43412 | 62720 | 1.015 | 0.394 | 0.254 | 0.367
| | 2001 | 総 計 | 173144 | 49325 | 0.285 | 181681 | 65414 | 48074 | 68193 | 1.049 | 0.378 | 0.278 | 0.394
| | 2001(内訳) | 国立大学 | 61009 | 20162 | 0.330 | 39991 | 17568 | 14708 | 7715 | 0.655 | 0.288 | 0.241 | 0.126
| | 公立大学 | 10747 | 3336 | 0.310 | 8293 | 3580 | 2469 | 2244 | 0.772 | 0.333 | 0.230 | 0.209
| | 私立大学 | 79764 | 19076 | 0.239 | 98861 | 33107 | 22646 | 43108 | 1.239 | 0.415 | 0.284 | 0.540
| | 放送大学 | 73 | 38 | 0.521 | 2359 | 1898 | 131 | 330 | 32.315 | 26.000 | 1.795 | 4.521
| | 国立短大 | 533 | 203 | 0.381 | 1704 | 680 | 848 | 176 | 3.197 | 1.276 | 1.591 | 0.330
| | 公立短大 | 1776 | 515 | 0.290 | 2677 | 1219 | 887 | 571 | 1.507 | 0.686 | 0.499 | 0.322
| | 私立短大 | 13202 | 4552 | 0.345 | 24742 | 6391 | 5682 | 12669 | 1.874 | 0.484 | 0.430 | 0.960
| | 国立高専 | 3910 | 768 | 0.196 | 2436 | 662 | 599 | 1175 | 0.623 | 0.169 | 0.153 | 0.301
| | 公立高専 | 395 | 75 | 0.190 | 226 | 48 | 59 | 119 | 0.572 | 0.122 | 0.149 | 0.301
| | 私立高専 | 168 | 9 | 0.054 | 43 | 0 | 11 | 32 | 0.256 | 0.000 | 0.065 | 0.190
| | 共同利用 | 1567 | 591 | 0.377 | 349 | 261 | 34 | 54 | 0.223 | 0.167 | 0.022 | 0.034
| |
文部科学省 『学校教員統計調査報告書』 (各年度,調査方法は1986年度より前は毎回変更) より作成.区分は,2001年度のものを過去に遡って援用したが,表における区分と『統計調査』における区分の対応は次の通り.
| 表における区分 | 『統計調査』における区分 | 単位
| | 専任教員 (A) | 本務教員 | 人 (実人数)
| | 兼任講師 (A*) | 教員本務者のうち兼務している者 (大部分は大学などで非常勤講師) | 人 (実人数)
| | 非常勤講師 (B) | 兼務教員 | 件 (延べ人数)
| | 兼任講師 (C) | 大学・短大・高専の教員からの兼務教員 | 件 (延べ人数)
| | 兼業講師 (D) | 専修各種その他の学校教員,研究所の研究員,その他の職業からの兼務教員 | 件 (延べ人数)
| | 専業非常勤講師 (E) | 本務なしの兼務教員 | 件 (延べ人数)
| |
※B = C+D+E
表で省略した非常勤講師の区分「不明・無回答(その他)」部分は,1977年22857件,1980年区分なし,1983年9529件,1986年3722件,1989年108件,1992年9件で,1995年以後は0件または区分なしである.「本務なし」の兼務教員 (表のE部分) の区分は,1986年の調査から設定されている.なお,表は『大学危機と非常勤講師運動』(こうち書房) 資料編の定義に従って作り直した.
大学,短大の教員数の変遷
| | 大学 | 短大 |
| 年度 | 専任教員 | 非常勤講師 | うち非専任教員 | 全教員の中の
非常勤講師の割合 | 非常勤講師の中の
非専任教員の割合 | 専任教員 | 非常勤講師 | うち非専任教員 | 全教員の中の
非常勤講師の割合 | 非常勤講師の中の
非専任教員の割合
| | A | B | C | B/(A+B) | C/B | A' | B' | C' | B'/(A'+B') | C'/B'
| | 1955 | 38010 | 13759 | 4664 | 26.6% | 33.9% | 5505 | 6695 | 930 | 54.9% | 13.9%
| | 1960 | 44434 | 16587 | 5447 | 27.2% | 32.8% | 6394 | 7262 | 1148 | 53.2% | 15.8%
| | 1965 | 57445 | 25759 | 8462 | 31.0% | 32.9% | 9321 | 11130 | 1870 | 54.4% | 16.8%
| | 1970 | 76275 | 42696 | 10485 | 35.9% | 24.6% | 15320 | 17444 | 3477 | 53.2% | 19.9%
| | 1975 | 89648 | 57637 | 19956 | 39.1% | 34.6% | 15557 | 20367 | 7108 | 56.7% | 34.9%
| | 1980 | 102989 | 65750 | 27540 | 39.0% | 41.9% | 16372 | 22678 | 10663 | 58.1% | 47.0%
| | 1981 | 105117 | 69312 | 28514 | 39.7% | 41.1% | 16696 | 24201 | 11166 | 59.2% | 46.1%
| | 1982 | 107422 | 70675 | 29790 | 39.7% | 42.2% | 16866 | 24722 | 11659 | 59.4% | 47.2%
| | 1983 | 109139 | 72147 | 31077 | 39.8% | 43.1% | 17202 | 25708 | 12315 | 59.9% | 47.9%
| | 1984 | 110662 | 74266 | 32566 | 40.2% | 43.9% | 17411 | 26649 | 12856 | 60.5% | 48.2%
| | 1985 | 112249 | 76767 | 34524 | 40.6% | 45.0% | 17760 | 27193 | 13398 | 60.5% | 49.3%
| | 1986 | 113877 | 78856 | 36044 | 40.9% | 45.7% | 18205 | 28375 | 14207 | 60.9% | 50.1%
| | 1987 | 115863 | 81171 | 36951 | 41.2% | 45.5% | 18774 | 29988 | 15182 | 61.5% | 50.6%
| | 1988 | 118513 | 83926 | 38489 | 41.5% | 45.9% | 19264 | 31501 | 16381 | 62.1% | 52.0%
| | 1989 | 121140 | 87140 | 40059 | 41.8% | 46.0% | 19830 | 32639 | 17208 | 62.2% | 52.7%
| | 1990 | 123838 | 90113 | 40884 | 42.1% | 45.4% | 20489 | 33755 | 17728 | 62.2% | 52.5%
| | 1991 | 126445 | 94866 | 44329 | 42.9% | 46.7% | 20933 | 35567 | 18617 | 63.0% | 52.3%
| | 1992 | 129024 | 98673 | 46712 | 43.3% | 47.3% | 21170 | 35804 | 19272 | 62.8% | 53.8%
| | 1993 | 131833 | 103652 | 50092 | 44.0% | 48.3% | 21111 | 37044 | 20588 | 63.7% | 55.6%
| | 1994 | 134849 | 107688 | 53790 | 44.4% | 49.9% | 20964 | 37879 | 21485 | 64.4% | 56.7%
| | 1995 | 137464 | 112668 | 57532 | 45.0% | 51.1% | 20702 | 38245 | 22132 | 64.9% | 57.9%
| | 1996 | 139608 | 117818 | 62195 | 45.8% | 52.8% | 20294 | 38299 | 22770 | 65.4% | 59.5%
| | 1997 | 141782 | 123916 | 66732 | 46.6% | 53.9% | 19885 | 38006 | 23118 | 65.7% | 60.8%
| | 1998 | 144310 | 128370 | 71010 | 47.1% | 55.3% | 19040 | 37380 | 22695 | 66.3% | 60.7%
| | 1999 | 147579 | 132776 | 75105 | 47.4% | 56.6% | 18206 | 36146 | 21960 | 66.5% | 60.8%
| | 2000 | 150563 | 137568 | 80043 | 47.7% | 58.2% | 16752 | 33852 | 21237 | 66.9% | 62.7%
| | 2001 | 152572 | 143047 | 84376 | 48.4% | 59.0% | 15638 | 31892 | 20366 | 67.1% | 63.9%
| | 2002 | 155050 | 149388 | 90414 | 49.1% | 60.5% | 14491 | 30094 | 19486 | 67.5% | 64.8%
| |
文部省『学校基本調査報告書』 (各年度) より作成.専任教員は実人数,非常勤講師は辞令件数による延べ人数.この表の用語と『基本調査』の用語の対応は以下の通り.専任教員=本務教員,非常勤講師=兼任教員,非常勤講師のうち非専任教員=教員以外からの兼務教員
グラフ1 教員数の変遷 (大学)
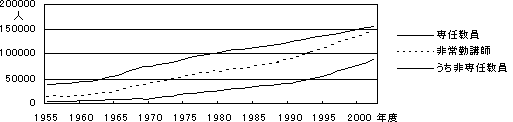
グラフ2 教員数の変遷 (短大)
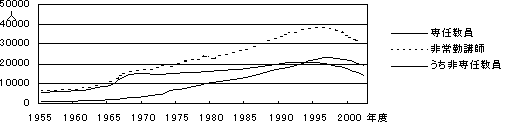
グラフ3 非常勤講師の割合の変遷 (大学)
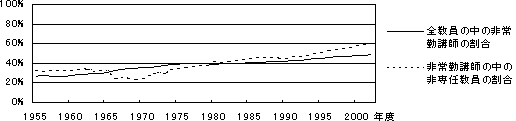
グラフ4 非常勤講師の割合の変遷 (短大)
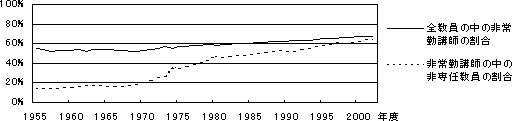
※グラフ1〜4は上記データより作成
国立大学における非常勤講師の給与
金田誠一議員の国会における質問・要求に応じて,2002年12月13日に文部科学省が金田議員にFAX送信したものは以下の通り.
非常勤講師の給与について
非常勤講師の勤務1時間あたりの単価については,当該職員を常勤講師として採用した場合に受けることとなる俸給月額による勤務1時間あたりの単価を基に,講義のための準備,学生に対する研究指導等の必要性を考慮し,各大学において,予算の範囲内で決定し,支給している.
(1時間単価額の具体例)14.12.1現在
| 級・号俸 |
大卒後の経験年数 |
常勤講師の給与 (円) |
国立A大学の非常勤講師の
1時間単価額 (円)
| | 俸給月額 |
1時間あたりの単価額 |
| 教(一)2-2 | 0.0 | 203,800 | 1,316 |
経験年数0.0〜4.11
4,350
| | 2-3 | 1.0 | 212,800 | 1,375 |
| 2-4 | 2.0 | 221,900 | 1,433 |
| 2-5 | 3.0 | 231,700 | 1,497 |
| 2-6 | 4.0 | 241,300 | 1,559 |
| 2-7 | 5.0 | 254,100 | 1,641 |
経験年数5.0〜9.11
5,100
| | 3-2 | 6.0 | 268,500 | 1,734 |
| 3-3 | 7.0 | 281,400 | 1,818 |
| 3-4 | 8.0 | 295,200 | 1,907 |
| 3-5 | 9.0 | 309,200 | 1,997 |
| 3-6 | 10.0 | 323,100 | 2,087 |
経験年数10.0〜14.11
5,910
| | 3-7 | 11.0 | 336,500 | 2,174 |
| 3-8 | 12.0 | 350,000 | 2,261 |
| 3-9 | 13.0 | 363,100 | 2.346 |
| 3-10 | 14.0 | 373,000 | 2,410 |
| 3-11 | 15.0 | 383,100 | 2,475 |
経験年数15.0〜19.11
6,570
| | 3-12 | 16.0 | 392,800 | 2,538 |
| 3-13 | 17.0 | 401,500 | 2,594 |
| 3-14 | 18.0 | 410,000 | 2,649 |
| 3-15 | 19.0 | 417,700 | 2,698 |
| 3-16 | 20.0 | 425,200 | 2,747 |
経験年数20.0〜24.11
7,220
| | 3-17 | 21.0 | 432,300 | 2,793 |
| 3-18 | 22.0 | 439,500 | 2,839 |
| 3-19 | 23.0 | 445,500 | 2,878 |
| 3-20 | 24.0 | 450,400 | 2,910 |
| 3-21 | 25.0 | 454,900 | 2,939 |
経験年数25.0〜29.11
8,060
| | 3-22 | 26.0 | 458,000 | 2,959 |
| 3-23 | 27.0 | 461,100 | 2,979 |
| 3-24 | 28.0 | 464,100 | 2,998 |
| 3-25 | 29.0 | 467,200 | 3,018 |
| 3-26 | 30.0 | 470,200 | 3,038 |
経験年数30.0〜
8,680
| | 3-27 | 31.0 | 473,300 | 3,058 |
| 3-28 | 32.0 | 476,400 | 3,078 |
|
※常勤講師の1時間あたりの単価額及び非常勤講師の1時間単価額には,調整手当相当給与分を含む。
[常勤講師の1時間あたりの単価算出式]
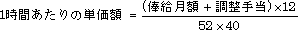
●非常勤職員の給与について
平成13年3月26日 12 文科人第242号
官房長,文教施設部長,国際統括官,各局長,各国立学校長,各大学共同利用機関長,大学入試センター所長,大学評価・学位授与機構長,国立学校財務センター所長,文部科学省各施設等機関長,日本学士院長,水戸原子力事務所長,各都道府県知事,各都道府県教育委員会あて文部科学省大臣官房人事課長通知
[沿革]平成一三年三月三〇日 一二文科人第二五八号改正
このことについて,下記のとおり定めましたので,平成十三年一月六日以降はこれによりお取り扱い願います.なお,これに伴い「非常勤職員の給与について」(昭和三十七年六月二十八日付け文人給第一一九号文部省大臣官房人事課長通知),「非常勤職員の給与の取り扱いについて」(平成十年三月二十七日付け文人給第三一四号文部省人事課長通知) 及び「常勤的非常勤職員の取扱要領」 (昭和六十年三月三十一日付け科技秘第七二七号科学技術庁大臣官房秘書課長通知) は廃止します.
なお,非常勤職員に支給する給与は,従前どおりすべて既定予算の範囲内で支給することとします.
記
1 非常勤職員の勤務一時間当りの給与 (以下「時間給」という.) または勤務一日当りの給与 (以下「日給」という.) は,次に掲げるところによるものとすること.
(1) 講師である非常勤職員については,その者を常勤の講師として採用した場合に受けることとなる俸給月額および調整手当の額を基礎として次の算式により算出した額の範囲内の額をもって時間給とする.
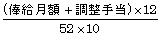
(2) 医師,歯科医師,学校医および学校歯科医である非常勤職員については,その者を常勤の医師または歯科医師として採用した場合に受けることとなる俸給月額および調整手当の額を基礎として,次の算式により算出した額の範囲内の額をもって時間給とする.
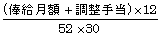
なお,採用困難等のため特に必要がある場合の俸給月額は,人事院規則九−八第一五条中「一八月」とあるのを「一二月」と読み替え,同条ただし書の規定がないものとして同条の規定の例によることができるものとし,同規則別表第二医療職俸給表(一)級別資格基準表に定める必要経験年数を有する者については,二級相当に格付できるものとする.
また,上記算式中の「一二」に年間の特別給支給割合を加えることができるものとする.(これにより算出した額に一〇〇円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする.)
(3) 上記(1)および(2)のほか,一日につき八時間を超えない範囲内で日々雇い入れられる非常勤職員 (以下「日々雇用職員」という.) については,その者を常勤の職員として採用した場合に受けることとなる俸給月額および調整手当の額を基礎として,次の算式により算出した額の範囲内の額をもって日給とする.
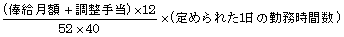
(4)上記(1)および(2)のほか,常勤職員の一週間当たりの勤務時間の四分の三をこえない範囲内で勤務する非常勤職員については,その者を常勤の職員として採用した場合に受けることとなる俸給月額および調整手当の額を基礎として,次の算式により算出した額の範囲内の額をもって時間給とする.
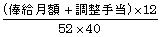
なお,職務の特殊性等によりその採用が著しく困難である場合等この時間給算出の方法によることを適当としない場合 (いずれも,一時的な業務を処理するため一月以内の期間勤務する者を採用する場合に限る.) は,上記にかかわらず,人事院規則九−八第一五条第一項ただし書等の規定により算出される初任給の最高の号俸 (以下「最高号俸」という.) にかかる時間給 (算式は,上記の算式を適用するものとする.) の範囲内で適当と認められる一定の額をもって時間給とすることができる.
(5) 非常勤職員のうち,人事院規則九−六 (俸給の調整額) の別表に掲げる職員と同様の職務を行なうものと認められる者で,かつ勤務命令等が常勤の職員の例により取り扱われている者については,その者を常勤の職員として採用した場合に受けることとなる俸給の調整額とこれに対する調整手当を合算した額を,時間給または日給の算出の基礎となる額に加算することができる.
2 非常勤職員の採用が困難である場合その他特別の事由がある場合において,前記一に規定する時間給または日給の額をこえる額に決定しようとするときは,次に掲げる書類を添えて文部科学大臣あて協議するものとすること.
なお,国立学校設置法施行規則(昭和三十九年四月一日付け文部省令第一一号)第三十条の五に定める寄附講座及び同規則第三十条の六に定める寄附研究部門の教員については,決定される日給額を基礎とした年額が常勤として採用した場合に得られる号俸の一号俸上位の俸給月額を基礎とした年額の範囲内である場合に限り,文部科学大臣あて協議があったものとして取り扱うことができる.
(以上)
丸子警報器事件判決の意義
臨時社員の賃金格差を是正させた,わが国初の判決 (1996年3月15日長野地裁上田支部)
事実
原告ら28名は,自動車の警報器メーカーの製造ラインで働くパート女子社員であった.臨時社員として2か月ごとの有期雇用契約を反復・継続する形で更新しながら,それぞれ4年から25年勤務してきた.仕事内容,勤務時間,勤務日数や社内研修サークルへの参加など他の女子正社員とほとんどかわることのない勤務状況であった.ところが同じ勤続年数でありながら,パート女子社員と女子正社員との間では,それぞれ給与 (65%) 一時金 (59%) 退職金 (18%) という著しい賃金格差が実態としてあった.原告らは,この賃金格差は,労働基準法4条 (男女同一賃金原則) 3条 (均等待遇原則) 違反であり,同一 (価値) 労働同一賃金の原則という公序 (民法90条) に違反するとして,正社員との賃金格差分に対する損害賠償の支払いを求めて1993年に提訴した.
判決内容
(1) 同一 (価値) 労働同一賃金の原則が労働関係を規律する一般的な法規範として存在していると認めることはできないが,不合理な賃金格差を是正するための指導理念としては考慮すべき場合がある.
(2) 労働基準法3条や4条の規定の根底には,およそ人はその労働に対し等しく報われなければならないという均等待遇の理念が存在するのであり,それは人格の価値を平等とみる市民法の普遍的な原理と考えるべきものである.
(3) 本件のように,女性正社員との顕著な賃金格差を維持拡大しつつ長期間の雇用を継続したことは同一 (価値) 労働同一賃金の原則の根底にある均等待遇の理念に違反する格差であり,公序良俗違反として違法となる.
(4) 均等待遇の理念は抽象的なものであり,均等に扱うための前提となる諸要素の判断には幅がある.その幅の範囲内における待遇の差に使用者の裁量の余地はあるものの,原告らの賃金が同じ勤務年数の女性正社員の八割以下となるときは,許容される賃金格差の範囲を明らかに越え,その限度において使用者の裁量が公序良俗違反として違法となると判断すべきである.
判決以後の丸子警報器
労働者側,使用者側双方とも高等裁判所に控訴したが,その後1999年に和解した.和解の内容は
(1) 臨時社員の賃金制度を日給制から月給制にかえる
(2) 平成16年までに正社員の9割前後の水準まで給与を是正する
(3) 賞与は正社員と同じ計算方法にする
(4) 退職金について正社員と同一規定を適用する
(5) 解決金(1600万円)を支払う
である.つまり臨時社員の労働条件は実質的に正社員とほぼ同等になった.
判決の社会的意義
1.裁判所が,正社員と臨時社員(パート)との賃金格差の実態を直視し,はじめて,その矛盾を解決するための判断基準を明確に示した.つまり雇用形態に基づく賃金格差も一定の範囲を越えると公序良俗違反となる場合があるということである.現にこの判決以後同様な臨時職員の賃金格差の是正や具体的な待遇改善がはかられた例もある.
2.パート労働者の労働条件改善にむけた本格的な議論のきっかけとなった.とくに判決で指摘された均等待遇のあり方を中心に,政府,使用者,労働組合,市民団体,国会議員などが活発に議論をはじめるようになった(パートタイム労働研究会報告など).この背景には,わが国ではパート労働者が千二百万人をこえており,会社におけるパートタイマーの位置付けが2極化 (正社員なみの働き方と臨時社員としての働き方) している実情がある.また欧米諸国などのようにパート労働者の法的保護 (均等待遇保障やフルタイマーとパートタイマーとの就業の転換を容易にすることなど) を積極的におこなっていることの影響もある.パート労働者は今後ともいっそうの量的増加が見込まれる.したがって,均等待遇のあり方については幅広く,深い議論がいっそうもとめられる.
丸子警報器事件についてもっと知りたい人のために
1.丸子警報器事件・長野地裁上田支部判決 (1996年3月15日) については,雑誌『労働判例』690号32頁以下参照.
2.丸子警報器の事件経過については,丸子争議支援共闘/丸子支援・パートまもる全国連絡会編『パート・臨時だって労働者−新しい扉ひらいた丸子警報器の仲間』 (学習の友社,2000年6月刊)を参照.
(WT)
連絡先
サマリーと目次
序
1 回答者の構成
2 働き方
3 収入支出
4 健康保険,年金
5 雇用問題
6 全般
自由記述
付録